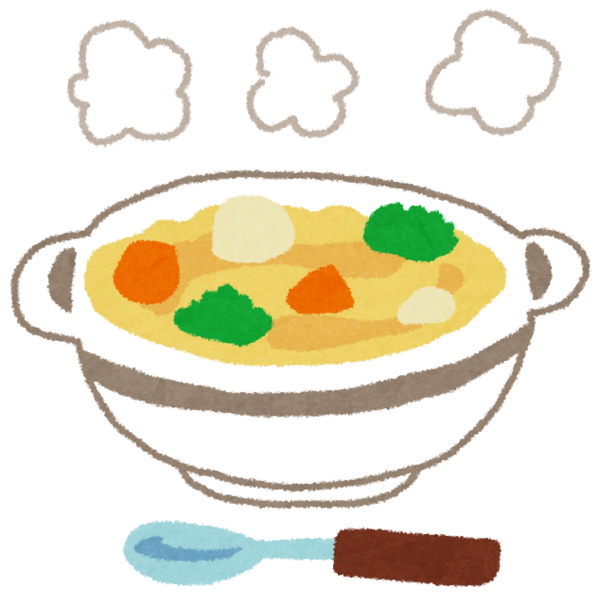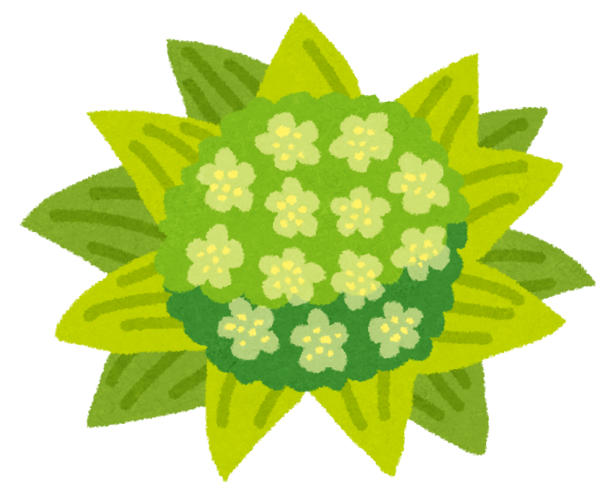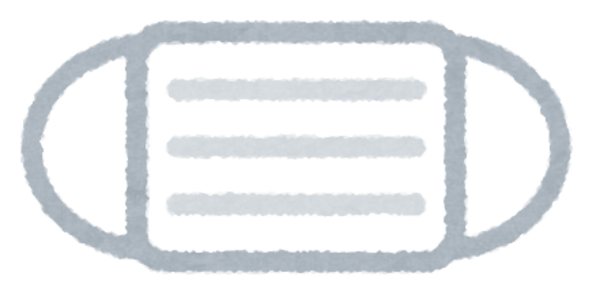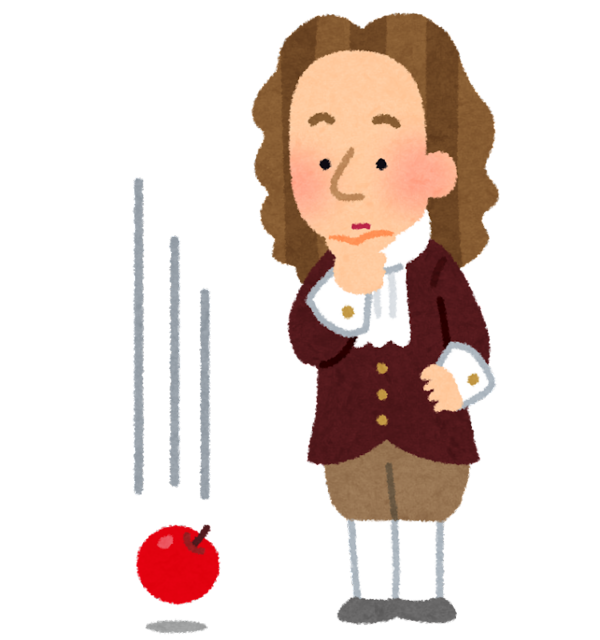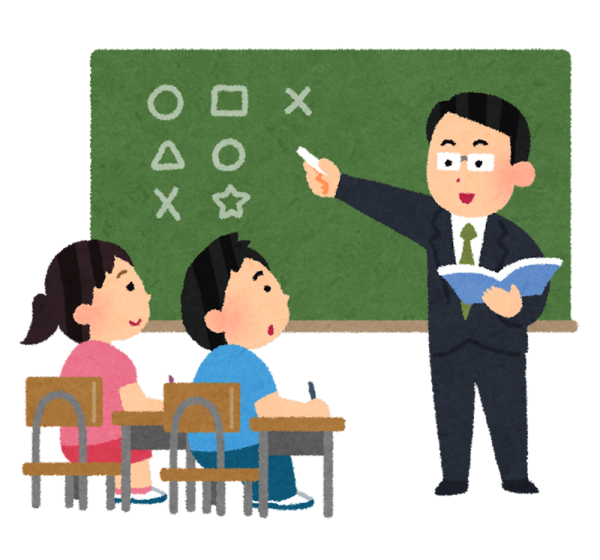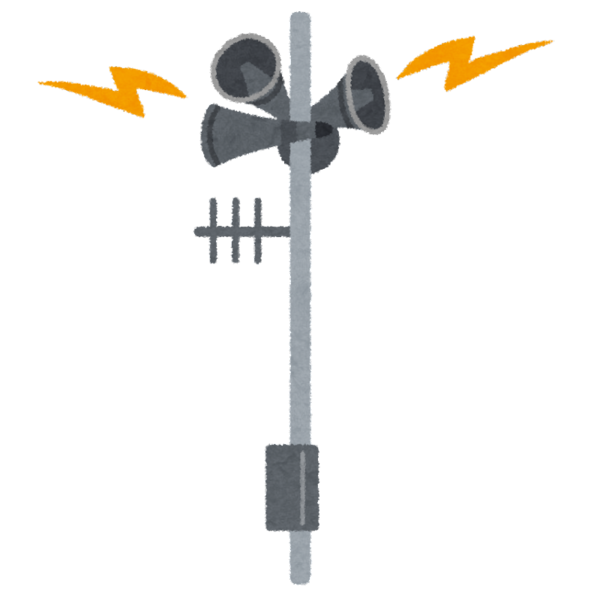4月はるやすみ🍓いちごクラス🍓(預かり保育)給食メニュー
R5.3.17 あおば 年中少
19日に第57回卒園式を挙行いたします。ねんちょうぐみのみなさん御卒園です。 1人ひとりの姿を見ていると、とても逞しく立派に見えます・・・・・面接した時のことを思い出したり、今までのことを思い出したり・・・・もうご卒園です。そして、早いもので今年度も来週の22日で修了です。子どもたちと過ごした日々を振り返り、良いものは伸ばしながら来年度に向かい歩んでいきます。
まだ収束していないコロナ禍の中でも一年間、先生やお友達と一緒に遊んだり、笑ったり、泣いたり、時々けんかしたり、仲直りしたり、お母さんの作ってくれた『お弁当』を嬉しそうに見せてくれたり、運動会では 、一生懸命走ったり、踊ったり、カレーライスをみんなと一緒においしそうに食べたり、 発表会では、みんなで頑張って発表したり、クリスマス会ではサンタクロースと出会ったり、節分では悪い鬼に豆をぶつけて追い返してくれたり、ちょっぴり怖くて泣いてしまったり、いろいろな経験を大切に、またこれからあかるく!つよく!たくましく!共に成長していきたいと思います。一年間、送り迎え等していただいたり子どもたちの大好きな「おべんとう」を作っていただいたりしたお母さん、ご理解ご協力していただいたお父さんありがとうございます。
のびゆく姿
幼稚園生活の中で担任から見て感じた一年間の成長を記録しました「のびゆく姿」を修了式の日にお子さんにお渡しします。5領域(健康)(人間関係)(環境)(言葉)(表現)を踏まえながら指導の重点をそれぞれ設定し、目標に近づくように指導しました。4月からの成長の記録です。 3学期は園へ戻す必要はございませんのでご家庭で保管下さい。
給食費等の値上げについて
諸物価の値上げに伴いまして来年度より給食費が一食340円から360円に値上げとなります。
ご了承ください。他のものにつきましても価格改定がありましたら、その都度お知らせいたします。
はるやすみ
4月8日進級式まで「はるやすみ」です。子どもにとってはなつやすみもふゆやすみも長期やすみは楽しくウキウキします。それにも増してはるやすみは成長の喜びと希望があります『大きい組になったら・・・するんだ』『小さい組さんと遊んであげるんだ』という話を子どもからよくききます。これは成長の自覚であり、進級する喜びであり、誇りでもあります。この気持ちを一層広げてあげることが大切です。上の空で聞かれた子どもの気持ちを考えてみると寂しい気持ちで、だんだん話さなくなってきてしまいます。
子どもと話すと言うことは、子どもの気持ちになって話し相手になってあげることです。同時に子どもに 「あっそうか!こうするんだね!」というように気付かせてあげることが大切です。気付く事によって次の意欲が湧いてきて、自信を持つようになります。
はるやすみのせいかつ
おれい
これで私の令和4年度保護者のみなさまへの「あおば」の作成も何もなければ納めさせていただきます。ご期待にそえないところもあったかと思います。多にしても少にしても、ご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。
園 長 磯 貝 孝
20日(月曜日)は卒園式の振替休日です。
まだ収束していないコロナ禍の中でも一年間、先生やお友達と一緒に遊んだり、笑ったり、泣いたり、時々けんかしたり、仲直りしたり、お母さんの作ってくれた『お弁当』を嬉しそうに見せてくれたり、運動会では 、一生懸命走ったり、踊ったり、カレーライスをみんなと一緒においしそうに食べたり、 発表会では、みんなで頑張って発表したり、クリスマス会ではサンタクロースと出会ったり、節分では悪い鬼に豆をぶつけて追い返してくれたり、ちょっぴり怖くて泣いてしまったり、いろいろな経験を大切に、またこれからあかるく!つよく!たくましく!共に成長していきたいと思います。一年間、送り迎え等していただいたり子どもたちの大好きな「おべんとう」を作っていただいたりしたお母さん、ご理解ご協力していただいたお父さんありがとうございます。
のびゆく姿
幼稚園生活の中で担任から見て感じた一年間の成長を記録しました「のびゆく姿」を修了式の日にお子さんにお渡しします。5領域(健康)(人間関係)(環境)(言葉)(表現)を踏まえながら指導の重点をそれぞれ設定し、目標に近づくように指導しました。4月からの成長の記録です。 3学期は園へ戻す必要はございませんのでご家庭で保管下さい。
給食費等の値上げについて
諸物価の値上げに伴いまして来年度より給食費が一食340円から360円に値上げとなります。
ご了承ください。他のものにつきましても価格改定がありましたら、その都度お知らせいたします。
はるやすみ
4月8日進級式まで「はるやすみ」です。子どもにとってはなつやすみもふゆやすみも長期やすみは楽しくウキウキします。それにも増してはるやすみは成長の喜びと希望があります『大きい組になったら・・・するんだ』『小さい組さんと遊んであげるんだ』という話を子どもからよくききます。これは成長の自覚であり、進級する喜びであり、誇りでもあります。この気持ちを一層広げてあげることが大切です。上の空で聞かれた子どもの気持ちを考えてみると寂しい気持ちで、だんだん話さなくなってきてしまいます。
子どもと話すと言うことは、子どもの気持ちになって話し相手になってあげることです。同時に子どもに 「あっそうか!こうするんだね!」というように気付かせてあげることが大切です。気付く事によって次の意欲が湧いてきて、自信を持つようになります。
はるやすみのせいかつ
 できるだけ自分のことは自分でする習慣化
できるだけ自分のことは自分でする習慣化 - ものを大切にする・・・進級で新しいものを買うこともあると思います。大事に使わせるようにしましょう!
- 整理整頓を自分でやるように・・・整理整頓は、とかく依頼心が起こりがちです。子どもが自ら進んで行なう環境を創る工夫をお願いします。
- 挨拶がきちんとできるように・・・小さいときにこそ挨拶の習慣を身に付けましょう!
- お話を目を見て聞ける子に育てましょう!
おれい
これで私の令和4年度保護者のみなさまへの「あおば」の作成も何もなければ納めさせていただきます。ご期待にそえないところもあったかと思います。多にしても少にしても、ご覧いただきましてありがとうございました。またよろしくお願いします。
園 長 磯 貝 孝
20日(月曜日)は卒園式の振替休日です。
R5.3.15 あおば 卒園号
もうすぐ、御卒園
おとうさん、おかあさんが一生懸命育てた、お子さんの初めての集団生活の場ようちえんも卒園です。最近の年長組のみなさんは年中少組・ちゅーりっぷ組のおともだちの面倒を見たり、教えてあげたり、すっかり幼稚園ではおにいさん・おねえさんです。その子たちの卒園までの時間が砂時計の砂がサラサラと残り少ない事を教えてくれているかのように目前です。
入園してからコロナ渦が続き、マスクをつけての園生活、いろいろな体験や経験も制限され体験・経験させてあげられなかった事が名残惜しく、悔しい気持ちはありますが、そのような未練がある気持ちを大人が表したなら、子どももそれに従います。感染症とは怖いもの、このようなときは、こうゆう風にすることで安全や安心を取り戻すことができるということを、このようなときはどうしたらいいかということを順に教えてくれているような気がしています。このことによって、これから先、同じような事態が発生した時の教訓として記憶に留めなさい、普通の日常が人間にとってはどんなに大切な物かということを知らされているような感じです。
産まれてから産声を上げ、目が開き、笑い、ハイハイし、立ち上がり、歩き、表現を覚え、言葉を覚え、家庭から幼稚園に通い、家族ではいない友達や先生と一緒に遊んだり、笑ったり、泣いたり、ときどきケンカしたり、「ごめんなさい」「いいよ」と言って、すぐ仲直りしたり、お母さんのつくってくれたおべんとうを 嬉しそうに見せてくれたり、出来なかったことが、出来るようになったとき自慢して見せたり、プール遊びでは元気いっぱいはしゃいだり、運動会では、ゴール目指して一生懸命走ったり、踊ったり、おとまり会では、お母さんから離れて友達いっぱいで楽しんだり、時々寂しくなっちゃたり…発表会の劇では役を立派に演じたり、クリスマス会ではサンタクロースと出会って大喜びしたり、いろいろな「おもいで」とともに歩んでくれた23名の子どもたちの卒園です。幼稚園から小学校へと巣立ちます。
いよいよ4月からはピカピカの一年生、希望に向け成長したみんなを送り出すことは、とても喜ばしく、お祝いし、おめでたいことなのですが、なにかしら心に寂しいものが本当のところ感じてきてしまいます。
子ども達の活動の中には大人にも真似が出来ないほどのバイタリティや屈託のない人間関係、真剣な取り組みの姿、優しく豊かな心情の育ちをいくつとなく見る事が出来ます。家庭を離れて、子ども集団の中でこそ育ちあうエネルギーやパワーの素晴らしさ、その感動に打たれ 励まされ、教えられた時がいっぱいあります。本来、子どもは何かをやりたくてムズムズしているものですが、周囲の禁止や抑圧や規制が、その意欲を無くすことが多くあります。かといってなんでもやりたい放題にやらせればよいのとは違います。「口を出すな!手を出すな!目を離すな!」とよく言います。年長児にもなれば、よく見守っていると、けっこうよく判断し解決していく時があります。しかし、行きづまると危険な時もあります。そんな時にこそ大人の出番です。頑張って何かをやり遂げ、手助けを受けながらでも成し遂げたとき、大人にとっては何でもない事かも知れませんが、子どもにとっての発見や喜びや感動は大きなものです。それは特別な日や特別な場所というわけではなく、日常の生活の中に多くあると思います。どうかその感動や喜びを共にしてあげてください。共感の世界をなるべく多くつくってください。わざとらしくつくった事は子どもの方から愛想をつかされてしまいます。素直に素朴に共感に浸ることは非常に肝心な事です。
子どもたちはドンドン成長していきます。しかし何といっても、まだまだ幼い一面を沢山持っています。「ずいぶん、しっかりしたなぁ」と思う反面「あれっ!」と感じる事が多いはずです。結構大人びた事を言うかと思うと、甘ったれの心もたくさん持っています。弟や妹がお母さんに甘えているのをみれば自分も・・・とうらやましくなるものです。そんな時は「一年生になるのでしょ」とは言わずに、そっと抱えてあげて下さい。それだけで、きっと満足し安心して、いかにもお兄さんらしく、お姉さんらしく、自分で遊んだりもします。
子どもが大きくなるということは自立(自律)して、親からやがて離れていくことです。しかし、まだまだ、親によりかかりたい時期なのです。
だからこそ親の手のかかった物や食べ物、愛情のある言葉、スキンシップが大切です。大きくなってからだと遅すぎますし、嫌がられます。よりかかったり、離れてひとりで行動したり、またよりかかったりと、繰り返し繰り返して育っていくものです。どうか「まだまだ」と微笑みながら「ずいぶん大きくなったなぁ」という気持ちで、おおらかにお子さんをじっと見守って下さい。このおおらかさが子どもを育てていく親としての大切な態度です。
それとこれからはもっともっとお友達との関係が重要となります。生活していくこと、大きくなっていくことの楽しさや辛さを学んでいきます。くじけそうになったりあきらめたくなったり、そうかと思うと得意になったり、嬉しいことが続いたり、みんな育っていく「生命の力」になっていくのです。生きていくことの素晴らしさ、その意味や意義、みんなで協力する事。ズルはしていけないこと、人はぶたないこと、おかたづけすること、悪いことをしたら謝ること、食事の前には手を洗うこと、挨拶をすること、返事をすること、自分の気持ちを伝える事、少し絵を描き、歌い、遊び、楽しみ、病気にならないように注意すること,交通安全や火の用心や災害に 気をつけること、手をつないで、離れ離れにならないこと、めそめそばかりしていては前に進めないこと・・・いろいろなことを卒園する子どもたち一人一人が、どんな気持ちで日々を送ればいいのか、人間として本当に知っていなくてはならない事を日々の生活の中でこれからも、少しずつでも身に付けていただきたいと思っています。
年月が過ぎ、みんなが大きくなり青葉幼稚園に通っていた時の事が懐かしく思ったときでも笑ったり、喜んだり、面白がったり、頑張ったり、いろいろな子どもたちの声のする暖かい場所で在り続けたいと思います。
明るく!強く!たくましく!成長していただきたいと強く願います。
子どもたちの大好きな「おべんとう」をつくっていただいた、お母さん、ご理解ご協力いただいた、お父さん 本当にありがとうございました。
そして幼稚園で一緒に歩み素晴らしい笑顔をくれた子ども達に深く感謝いたしますと共に、いつまでも真っ直ぐにものを見る輝いた目、輝く気持ち、知的好奇心を 持ちつづけてもらいたいと強く、強く卒園生にお願い致します。
卒園式を間近にし、みな様方とともに、お子様の成長を喜び、お祝い申し上げ心身一層の成長を期待します。
おめでとうございます!
・お渡ししました御案内のとおり挙行いたします。
*式当日の朝7時40分から8時30分の間に連絡アプリで検温・健康状態アンケートを実施しますのでご協力をお願いいたします。
・卒園生の服装は制服・制帽着用でジャージ以外の服装でお願いします。
御 礼
これで私の令和4年度第57回卒園生保護者の皆様方に送っていた「あおば」の作成もこれで納めさせて頂きます。今、幼稚園はこうです、こうゆう風に進めて行きたいです、こうしています。 家族として子どもと歩んでいくのはこうゆうものではないでしょうか・・・ということを言葉で伝えられない分、文字で少しでも伝えたいと、振り返ったり、思い浮かべたり、同じ文でも繰り返し伝えたり、考えたりしていることを立場上、本当の自分よりも大きく大きく背伸びしながら文章にしていました。
表現上、自己満足と反省するときもあります。ご理解していただけなかったことも、なにを言いたいんだ!と思う所も多くあったかと思いますが、これが無ければ私立幼稚園の「意味無し」と私は思っております。
ともあれ「あおば」多にしても少にしてもご覧いただき誠にありがとうございました。
卒園生の子ども達が立派な親になって読んでもらう日を期待しています。
卒園生諸君!
いつまでも君達を力強く
応援しております!
あかるく!つよく!たくましく!
ちとせあおばようちえん
園長 磯貝 孝
おとうさん、おかあさんが一生懸命育てた、お子さんの初めての集団生活の場ようちえんも卒園です。最近の年長組のみなさんは年中少組・ちゅーりっぷ組のおともだちの面倒を見たり、教えてあげたり、すっかり幼稚園ではおにいさん・おねえさんです。その子たちの卒園までの時間が砂時計の砂がサラサラと残り少ない事を教えてくれているかのように目前です。
入園してからコロナ渦が続き、マスクをつけての園生活、いろいろな体験や経験も制限され体験・経験させてあげられなかった事が名残惜しく、悔しい気持ちはありますが、そのような未練がある気持ちを大人が表したなら、子どももそれに従います。感染症とは怖いもの、このようなときは、こうゆう風にすることで安全や安心を取り戻すことができるということを、このようなときはどうしたらいいかということを順に教えてくれているような気がしています。このことによって、これから先、同じような事態が発生した時の教訓として記憶に留めなさい、普通の日常が人間にとってはどんなに大切な物かということを知らされているような感じです。
産まれてから産声を上げ、目が開き、笑い、ハイハイし、立ち上がり、歩き、表現を覚え、言葉を覚え、家庭から幼稚園に通い、家族ではいない友達や先生と一緒に遊んだり、笑ったり、泣いたり、ときどきケンカしたり、「ごめんなさい」「いいよ」と言って、すぐ仲直りしたり、お母さんのつくってくれたおべんとうを 嬉しそうに見せてくれたり、出来なかったことが、出来るようになったとき自慢して見せたり、プール遊びでは元気いっぱいはしゃいだり、運動会では、ゴール目指して一生懸命走ったり、踊ったり、おとまり会では、お母さんから離れて友達いっぱいで楽しんだり、時々寂しくなっちゃたり…発表会の劇では役を立派に演じたり、クリスマス会ではサンタクロースと出会って大喜びしたり、いろいろな「おもいで」とともに歩んでくれた23名の子どもたちの卒園です。幼稚園から小学校へと巣立ちます。
いよいよ4月からはピカピカの一年生、希望に向け成長したみんなを送り出すことは、とても喜ばしく、お祝いし、おめでたいことなのですが、なにかしら心に寂しいものが本当のところ感じてきてしまいます。
子ども達の活動の中には大人にも真似が出来ないほどのバイタリティや屈託のない人間関係、真剣な取り組みの姿、優しく豊かな心情の育ちをいくつとなく見る事が出来ます。家庭を離れて、子ども集団の中でこそ育ちあうエネルギーやパワーの素晴らしさ、その感動に打たれ 励まされ、教えられた時がいっぱいあります。本来、子どもは何かをやりたくてムズムズしているものですが、周囲の禁止や抑圧や規制が、その意欲を無くすことが多くあります。かといってなんでもやりたい放題にやらせればよいのとは違います。「口を出すな!手を出すな!目を離すな!」とよく言います。年長児にもなれば、よく見守っていると、けっこうよく判断し解決していく時があります。しかし、行きづまると危険な時もあります。そんな時にこそ大人の出番です。頑張って何かをやり遂げ、手助けを受けながらでも成し遂げたとき、大人にとっては何でもない事かも知れませんが、子どもにとっての発見や喜びや感動は大きなものです。それは特別な日や特別な場所というわけではなく、日常の生活の中に多くあると思います。どうかその感動や喜びを共にしてあげてください。共感の世界をなるべく多くつくってください。わざとらしくつくった事は子どもの方から愛想をつかされてしまいます。素直に素朴に共感に浸ることは非常に肝心な事です。
子どもたちはドンドン成長していきます。しかし何といっても、まだまだ幼い一面を沢山持っています。「ずいぶん、しっかりしたなぁ」と思う反面「あれっ!」と感じる事が多いはずです。結構大人びた事を言うかと思うと、甘ったれの心もたくさん持っています。弟や妹がお母さんに甘えているのをみれば自分も・・・とうらやましくなるものです。そんな時は「一年生になるのでしょ」とは言わずに、そっと抱えてあげて下さい。それだけで、きっと満足し安心して、いかにもお兄さんらしく、お姉さんらしく、自分で遊んだりもします。
子どもが大きくなるということは自立(自律)して、親からやがて離れていくことです。しかし、まだまだ、親によりかかりたい時期なのです。
だからこそ親の手のかかった物や食べ物、愛情のある言葉、スキンシップが大切です。大きくなってからだと遅すぎますし、嫌がられます。よりかかったり、離れてひとりで行動したり、またよりかかったりと、繰り返し繰り返して育っていくものです。どうか「まだまだ」と微笑みながら「ずいぶん大きくなったなぁ」という気持ちで、おおらかにお子さんをじっと見守って下さい。このおおらかさが子どもを育てていく親としての大切な態度です。
それとこれからはもっともっとお友達との関係が重要となります。生活していくこと、大きくなっていくことの楽しさや辛さを学んでいきます。くじけそうになったりあきらめたくなったり、そうかと思うと得意になったり、嬉しいことが続いたり、みんな育っていく「生命の力」になっていくのです。生きていくことの素晴らしさ、その意味や意義、みんなで協力する事。ズルはしていけないこと、人はぶたないこと、おかたづけすること、悪いことをしたら謝ること、食事の前には手を洗うこと、挨拶をすること、返事をすること、自分の気持ちを伝える事、少し絵を描き、歌い、遊び、楽しみ、病気にならないように注意すること,交通安全や火の用心や災害に 気をつけること、手をつないで、離れ離れにならないこと、めそめそばかりしていては前に進めないこと・・・いろいろなことを卒園する子どもたち一人一人が、どんな気持ちで日々を送ればいいのか、人間として本当に知っていなくてはならない事を日々の生活の中でこれからも、少しずつでも身に付けていただきたいと思っています。
年月が過ぎ、みんなが大きくなり青葉幼稚園に通っていた時の事が懐かしく思ったときでも笑ったり、喜んだり、面白がったり、頑張ったり、いろいろな子どもたちの声のする暖かい場所で在り続けたいと思います。
明るく!強く!たくましく!成長していただきたいと強く願います。
子どもたちの大好きな「おべんとう」をつくっていただいた、お母さん、ご理解ご協力いただいた、お父さん 本当にありがとうございました。
そして幼稚園で一緒に歩み素晴らしい笑顔をくれた子ども達に深く感謝いたしますと共に、いつまでも真っ直ぐにものを見る輝いた目、輝く気持ち、知的好奇心を 持ちつづけてもらいたいと強く、強く卒園生にお願い致します。
卒園式を間近にし、みな様方とともに、お子様の成長を喜び、お祝い申し上げ心身一層の成長を期待します。
おめでとうございます!
・お渡ししました御案内のとおり挙行いたします。
*式当日の朝7時40分から8時30分の間に連絡アプリで検温・健康状態アンケートを実施しますのでご協力をお願いいたします。
・卒園生の服装は制服・制帽着用でジャージ以外の服装でお願いします。
御 礼
これで私の令和4年度第57回卒園生保護者の皆様方に送っていた「あおば」の作成もこれで納めさせて頂きます。今、幼稚園はこうです、こうゆう風に進めて行きたいです、こうしています。 家族として子どもと歩んでいくのはこうゆうものではないでしょうか・・・ということを言葉で伝えられない分、文字で少しでも伝えたいと、振り返ったり、思い浮かべたり、同じ文でも繰り返し伝えたり、考えたりしていることを立場上、本当の自分よりも大きく大きく背伸びしながら文章にしていました。
表現上、自己満足と反省するときもあります。ご理解していただけなかったことも、なにを言いたいんだ!と思う所も多くあったかと思いますが、これが無ければ私立幼稚園の「意味無し」と私は思っております。
ともあれ「あおば」多にしても少にしてもご覧いただき誠にありがとうございました。
卒園生の子ども達が立派な親になって読んでもらう日を期待しています。
卒園生諸君!
いつまでも君達を力強く
応援しております!
あかるく!つよく!たくましく!
ちとせあおばようちえん
園長 磯貝 孝
3月13日〜19日週案(活動の予定)
あおば R5.3.10
ことしはびっくりするほどの大雪もなく、例年に比べると雪解けが早く、お外は何かしら春の匂いがするような今日この頃
3月に入り、日が過ぎるのがとても速く感じます。
15日[おわかれ会]19日「卒園式」です。年長組の子どもたちは、小学校に進学することを間近に控え、そのことを とても意識し始めています。年長児の子どもとあいさつを交わしたり、会話をしたりすると目の錯覚なのかな?と 想えるくらい入園したての顔が思い出されてくるのもこの時期です。
普段、普通に同じ空間で生活しているといろいろな事の連続で、繰り返しまた繰り返しで・・・大人はなにか物足りなさを感じたりすることもありますが、こどもと話していると希望や勇気をもらえます。「あしたはなにがあるのかなぁ〜」と尋ねてみると、いろいろな発想でいろいろな明るい答えが返ってきて「たのしみですねぇ〜」と伝えると、とてもうれしそうな 表情を見せてくれます。期待と希望のかたまりです。
子どもはなにげない日常の事を吸収して、なんとか頑張って真似てみたり、出来たときは心の中で自信をつけたり、嬉しすぎるとぴょんぴょん飛び跳ねちゃったりします。通いなれたスーパーマーケットに子どもを連れていくと周りの雰囲気を一生懸命に全集中でチラッ チラッと見て3回目にもなると大人では面倒なバーコード読みをしたがったりします。食堂やコンビニに連れていくと見ていないようでも、 大人では感じ取れない発見をしたり、とても喜んだりします。
大人には感じ取れないすばらしい発想があったり、反対に大人にとっては何でもないことでもとても不安になったりもします。子ども達はそれぞれ4月からの新しい環境に大丈夫そうに見えても、それぞれその体の内にはいろいろな期待やいろいろな不安を持っています。 笑顔で「いってらっしゃい!」「おかえりなさい!」をお願いします。 すぐに大きくなってしまいます。
がんばったでしょう
15日 おわかれかいの中で、全園児にがんばったでしょうを渡します。またPTAよりはんかちのぷれぜんとが出ていますので持ち帰らせます。
かいきんしょう
皆勤園児にかいきんしょうを卒園式・修了式でお渡します。
PTA活動 ありがとうございました。
本年度は諸行事等の自粛が多かったのですが、PTA会長をはじめPTA役員の皆様、保護者の皆様、いろいろとご協力ありがとうござました。子ども達に成り代わりましてお礼申し上げます。
マスク
3月13日から、マスクの着用は個人の選択が尊重されます。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることはいたしません。なお、来園される保護者の方にはマスクの着用を求めませんが、職員には 当面の間、園児対応の場面でのマスク着用を推奨します。
年長児保護者様
3月19日卒園式に於きましては2月17日にお配りしました「卒業式におけるマスクの取扱い等について」に記載されています国の方針に基づき、保護者の方はマスク着用でご臨席をお願いします。卒園生につきましては合唱・呼びかけの際はマスク着用としますのでマスクは持たせて又は着用させて登園をお願いします。入退場・証書授与の際はノーマスクです。
発見学習気づかせる伝え方 教え方・・・考える力
子どもにものごとを伝え教える場合、親とか先生が言葉によって伝え・教えてゆくのが普通の方法ですが、子どもが自分の経験を通して発見する、気づくという事が大切です。この点から子どもの自由な遊びという活動が重要だという事が 解ります。大人がいろいろな事を教える・教えないでは子どもの知識の量には違いが出てくるでしょう。しかし 単に物事をよく覚えているという事と創造的・生産的な思考ができるという事は全く関係が無く、そればかりか単に機械的に物事を覚えることばかりしていると柔軟なものの見方ができなくなり 自分で考えて解決法を発見することなどが 不得意なってしまいます。ですから子供がいろいろな事に疑問を抱いたりしたときに、つまらない事だと片づけてしまうのではなく、むしろ興味や疑問を育てるように援助してあげることが大切です。幼少期の頃から、こうした経験を豊富に持つことが問題を発見する能力を育てることになると思います。昔の人はこのような感覚を持つのはサンタクロースを信じる頃にまたことわざでは鉄は熱いうちに打ちなさいという言葉で表現していました。
3月に入り、日が過ぎるのがとても速く感じます。
15日[おわかれ会]19日「卒園式」です。年長組の子どもたちは、小学校に進学することを間近に控え、そのことを とても意識し始めています。年長児の子どもとあいさつを交わしたり、会話をしたりすると目の錯覚なのかな?と 想えるくらい入園したての顔が思い出されてくるのもこの時期です。
普段、普通に同じ空間で生活しているといろいろな事の連続で、繰り返しまた繰り返しで・・・大人はなにか物足りなさを感じたりすることもありますが、こどもと話していると希望や勇気をもらえます。「あしたはなにがあるのかなぁ〜」と尋ねてみると、いろいろな発想でいろいろな明るい答えが返ってきて「たのしみですねぇ〜」と伝えると、とてもうれしそうな 表情を見せてくれます。期待と希望のかたまりです。
子どもはなにげない日常の事を吸収して、なんとか頑張って真似てみたり、出来たときは心の中で自信をつけたり、嬉しすぎるとぴょんぴょん飛び跳ねちゃったりします。通いなれたスーパーマーケットに子どもを連れていくと周りの雰囲気を一生懸命に全集中でチラッ チラッと見て3回目にもなると大人では面倒なバーコード読みをしたがったりします。食堂やコンビニに連れていくと見ていないようでも、 大人では感じ取れない発見をしたり、とても喜んだりします。
大人には感じ取れないすばらしい発想があったり、反対に大人にとっては何でもないことでもとても不安になったりもします。子ども達はそれぞれ4月からの新しい環境に大丈夫そうに見えても、それぞれその体の内にはいろいろな期待やいろいろな不安を持っています。 笑顔で「いってらっしゃい!」「おかえりなさい!」をお願いします。 すぐに大きくなってしまいます。
がんばったでしょう
15日 おわかれかいの中で、全園児にがんばったでしょうを渡します。またPTAよりはんかちのぷれぜんとが出ていますので持ち帰らせます。
かいきんしょう
皆勤園児にかいきんしょうを卒園式・修了式でお渡します。
PTA活動 ありがとうございました。
本年度は諸行事等の自粛が多かったのですが、PTA会長をはじめPTA役員の皆様、保護者の皆様、いろいろとご協力ありがとうござました。子ども達に成り代わりましてお礼申し上げます。
マスク
3月13日から、マスクの着用は個人の選択が尊重されます。本人の意思に反してマスクの着脱を強いることはいたしません。なお、来園される保護者の方にはマスクの着用を求めませんが、職員には 当面の間、園児対応の場面でのマスク着用を推奨します。
年長児保護者様
3月19日卒園式に於きましては2月17日にお配りしました「卒業式におけるマスクの取扱い等について」に記載されています国の方針に基づき、保護者の方はマスク着用でご臨席をお願いします。卒園生につきましては合唱・呼びかけの際はマスク着用としますのでマスクは持たせて又は着用させて登園をお願いします。入退場・証書授与の際はノーマスクです。
発見学習気づかせる伝え方 教え方・・・考える力
子どもにものごとを伝え教える場合、親とか先生が言葉によって伝え・教えてゆくのが普通の方法ですが、子どもが自分の経験を通して発見する、気づくという事が大切です。この点から子どもの自由な遊びという活動が重要だという事が 解ります。大人がいろいろな事を教える・教えないでは子どもの知識の量には違いが出てくるでしょう。しかし 単に物事をよく覚えているという事と創造的・生産的な思考ができるという事は全く関係が無く、そればかりか単に機械的に物事を覚えることばかりしていると柔軟なものの見方ができなくなり 自分で考えて解決法を発見することなどが 不得意なってしまいます。ですから子供がいろいろな事に疑問を抱いたりしたときに、つまらない事だと片づけてしまうのではなく、むしろ興味や疑問を育てるように援助してあげることが大切です。幼少期の頃から、こうした経験を豊富に持つことが問題を発見する能力を育てることになると思います。昔の人はこのような感覚を持つのはサンタクロースを信じる頃にまたことわざでは鉄は熱いうちに打ちなさいという言葉で表現していました。
あおば R5.3.3
「1日入園」4月から新しくお友達になる新入園児の『1日入園』みんなで幼稚園の一日を紹介してもらいました。ご卒園を控えた年長組さん!大きい組さんになる年中組さん!大きく成長した年少組さん!もうすっかり、おにいさん、おねえさんです。
見ること 聞くことの 大切さ
子ども達を見ていて、へぇ〜とても立派なお話の聞き方が出来るんだな〜と思ったり、どうして聞くことが出来ないのかなぁ〜面白くないからなのかな〜と反省してみたりします。そのお話を聞かせる環境というのも大事ですが、そもそもはしっかり話を聞こうという姿勢が必要だと感じています。赤ちゃんを体の前側で抱っこして歩いているお母さんが良く、その赤ちゃんの顔を見ながら、楽しそうに「ほらぁ ブゥブゥだよぉ」「たのしいねぇ」って話しかけているのを見ると、きっと、その時、赤ちゃんはとっても嬉しそうにおかあさんの顔を見ているんだな〜と微笑ましい気持ちになります。
お話しを聞くときは、しっかりとお話をしている人の目を見て。その人が何を伝えようとしているかを感じ取りながら、話を聞く姿勢がとても大切ですし、人は本来その力を赤ちゃんの時から、備え持っているものです。小学校では一人一人が自分の机、そして椅子に座り担任の先生のお話を聞いたり、授業で先生から、いろいろな事を教えてもらったりします。
黒板に書いたものを見て書いて学習していきます。この基本的な事、ただ見様見真似では簡単にできることですが、何の為にするのかという事を考え方の中心に持っていなければ意味はありません。ちょっと難しかったり、わからなくなってしまって、ふざけたり、投げ出しちゃったりすることは簡単ですが、戻って同じことをもう一度となると興味も薄れてしまいます。水は高いところから低いところに流れると悪い例でよく例えられますが、水は熱があれば水蒸気になって上に行きます。お話しをする時の態度等ちょっとしたことから子どもの知的好奇心を広めましょう!
追 悼
今から12年前の3月11日午後2時46分東日本大震災が起こりました。多くの犠牲者・被害をもたらした震災で小さな子どもの命、多くの命を失うとともに甚大な被害を見せつけられ自然の力の恐ろしさも、現実のものとは思えない映像を見て「まさか!」という大きな悲しみや不安感を日本中で感じた震災でもあります。北海道でも大きな揺れを感じ、それが続くたびに不安になった記憶があります。地震や災害はいつ起こるかわからない場合が多いため、もしもの時に備えるにはどうしたらよいか!という事・命を預かっているところでは、そのとても痛ましいながらでも教訓から学び備えることの重要性を忘れないでいかなければいけないと強く思います。実際に被害にあわれた方々の追悼も含め、尊い犠牲の中の教訓を月日年月が経とうとも忘れないようにしましょう。
見ること 聞くことの 大切さ
子ども達を見ていて、へぇ〜とても立派なお話の聞き方が出来るんだな〜と思ったり、どうして聞くことが出来ないのかなぁ〜面白くないからなのかな〜と反省してみたりします。そのお話を聞かせる環境というのも大事ですが、そもそもはしっかり話を聞こうという姿勢が必要だと感じています。赤ちゃんを体の前側で抱っこして歩いているお母さんが良く、その赤ちゃんの顔を見ながら、楽しそうに「ほらぁ ブゥブゥだよぉ」「たのしいねぇ」って話しかけているのを見ると、きっと、その時、赤ちゃんはとっても嬉しそうにおかあさんの顔を見ているんだな〜と微笑ましい気持ちになります。
お話しを聞くときは、しっかりとお話をしている人の目を見て。その人が何を伝えようとしているかを感じ取りながら、話を聞く姿勢がとても大切ですし、人は本来その力を赤ちゃんの時から、備え持っているものです。小学校では一人一人が自分の机、そして椅子に座り担任の先生のお話を聞いたり、授業で先生から、いろいろな事を教えてもらったりします。
黒板に書いたものを見て書いて学習していきます。この基本的な事、ただ見様見真似では簡単にできることですが、何の為にするのかという事を考え方の中心に持っていなければ意味はありません。ちょっと難しかったり、わからなくなってしまって、ふざけたり、投げ出しちゃったりすることは簡単ですが、戻って同じことをもう一度となると興味も薄れてしまいます。水は高いところから低いところに流れると悪い例でよく例えられますが、水は熱があれば水蒸気になって上に行きます。お話しをする時の態度等ちょっとしたことから子どもの知的好奇心を広めましょう!
追 悼
今から12年前の3月11日午後2時46分東日本大震災が起こりました。多くの犠牲者・被害をもたらした震災で小さな子どもの命、多くの命を失うとともに甚大な被害を見せつけられ自然の力の恐ろしさも、現実のものとは思えない映像を見て「まさか!」という大きな悲しみや不安感を日本中で感じた震災でもあります。北海道でも大きな揺れを感じ、それが続くたびに不安になった記憶があります。地震や災害はいつ起こるかわからない場合が多いため、もしもの時に備えるにはどうしたらよいか!という事・命を預かっているところでは、そのとても痛ましいながらでも教訓から学び備えることの重要性を忘れないでいかなければいけないと強く思います。実際に被害にあわれた方々の追悼も含め、尊い犠牲の中の教訓を月日年月が経とうとも忘れないようにしましょう。